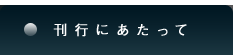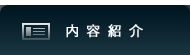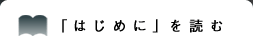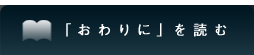-
1/3p
はじめに
萱野 稔人
健康でいるとき、私たちは身体というものをほとんど意識することがない。
しかし、ひとたび病気になったり怪我をしたりすれば、自分が身体という、意識によってはどうにもならない有機的物質からなりたっていることを強烈に意識させられる。東日本大震災が私たちにもたらしたのも、同じような意識の変化である。
現代の日本社会がいかに高度に人工化された近代文明によってつくられているとはいえ、2011年3月11日に起きた大地震と大津波は、私たちの生活が自然環境という、人間の力ではどうにもならない条件のもとでかろうじてなりたっていることを、あらためて私たちに思い知らせた。ひとたび大きな自然災害が起これば、私たちの生活は一気に崩壊してしまう。
東日本大震災は「千年に一度の大震災」といわれる。しかし、自然の長い歴史から見れば「千年」などという時間はほんの一瞬のことにすぎない。
その一瞬のあいだの、大きな自然災害のすき間をぬって、私たちの社会は発達してきた。自然環境がたまたま平穏状態にあって、人類がその「恵み」を活用できることが、私たちの文明のそもそもの基盤である。文明とは、まさに「かろうじて」というかたちでしか成立しえないものなのだ。
自然環境は私たちの文明をなりたたせもするし、壊しもする。人類は自然環境に翻弄されながら、同時にそれを活用し、豊かな社会を築いてきた。私たちの存在そのものが自然環境のなかに組み込まれているのだ。自然環境によってかたちづくられる存在の条件から、私たちは決して逃れることはできない。
-
2/3p
エネルギーについても同じことがいえる。
東日本大震災によって生じた福島第一原子力発電所の事故は、エネルギーの問題がいかに社会の根幹にかかわっているのかを私たちに自覚させた。
高効率のエネルギーを大量に利用できなければ私たちの社会は回っていかない、ということだけではない。原発事故によって脱原発の声はひじょうに高まったが、それと同時に、原発をやめるためには、電力供給のしくみから、産業そのもののあり方、そして権力の構造まで、大きく転換しなければならないことも明らかになった。つまり、どのようなエネルギーがもちいられるかによって社会のかたちまで規定されてくるのだ。
近代の物質文明は石炭や石油といった化石エネルギーや核エネルギーとともに成立してきた。それらのエネルギーがなければ近代文明はなりたちえなかったとさえいえるほどだ。この点からいえば、近代文明の特質はこれらのエネルギーによって根本的に規定されている。エネルギーとは文明にとっての存在の条件なのである。
自然環境もエネルギーも(もちろんエネルギーも自然環境のひとつの要素である)、私たちの社会をなりたたせている根本的な条件である以上、私たちは社会のなりたちをそれらの領域まで広げて考えなくてはならないはずだ。そうした思考の転換こそ、あれほど甚大な被害をもたらした東日本大震災によって要請されている知的態度にほかならない。
これまで、社会を考えるときに主流だったのは、社会をさまざまな外的要素から切り離して考えるという方法である。
-
3/3p
たとえば経済を考えるときには、市場を自然の制約や人口動態、政治的ファクターから切り離して考えることが、よりスマートで理論的な方法だとされてきた。権力を考えるときも同じである。暴力だとか富、人間の本性などから権力を論じることは、野暮ったいこととされてきた。
そうした方法のもとでは、考察の対象を他から切り離し、自立したモデルとして純化すればするほど、先端の理論だと考えられてきたのである。ちょうど健康なときには、自分が身体のもとで存在していることを忘れて、意識中心で自分のことを考えてしまうように。
本書の対談は、こうした知的傾向にあらがって、社会や文明のなりたちを自然環境やエネルギーの問題から考えることを主題としている。それこそが、東日本大震災のインパクトを受け止める知的方法だと考えるからだ。
もちろんそこではテクノロジーの問題も切り離せない。人類は、自然環境からただ一方的に影響を受けてきただけでなく、みずから自然環境に働きかけ、それを改変してきたからである。その延長線上に今回の原発事故もある。いわば、自然環境と人類の相互交渉のなかにいまの社会が直面している課題を位置づけようということだ。
この対談で私たちは、現代の日本社会が文明の転換点にあるという認識を共有している。現代の日本社会が抱えるいくつかの困難な問題は、大きくいえばその転換点に日本社会が位置していることに起因している。おそらく、東日本大震災はのちにこの転換点の象徴となるだろう。
では、その転換点とはどのようなものであり、どのような方向でその転換は図られるべきなのか。まさにこの問いこそ、本書の対談を貫く基底的な問いにほかならない。
- 1