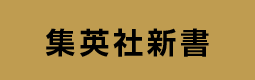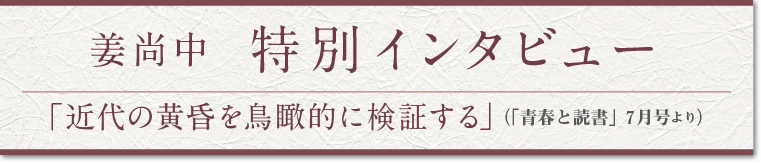内田樹氏と対談する姜尚中 撮影/三好祐司
思想家の内田樹さんと政治学者の姜尚中さん、リベラル派を代表するお二人が語り合った対談本『世界「最終」戦争論 近代の終焉を超えて』(集英社新書)が発売されました。混迷を深める世界情勢について、黄昏を迎えた近代という時代を丁寧に分析し、世界各国で現出している新しい政治現象に触れながら、ある大きな展望を示した一冊です。
今年からご出身地熊本の県立劇場の館長兼理事長に就任した姜さん。インタビューでは、四月に起きた熊本地震の緊迫した事態も引き合いに出しながら、この度の新刊にこめた思いをお話しいただきました。
聞き手=新書編集部/構成=増子信一
◆略歴◆
カン・サンジュン●1950年熊本県生まれ。東京大学名誉教授。専攻は政治学・政治思想史。2016年より熊本県立劇場館長兼理事長に就任。著書に『マックス・ウェーバーと近代』『オリエンタリズムの彼方へ』『ナショナリズム』『在日』『母─オモニ─』『心』『悩む力』『悪の力』『漱石のことば』等多数。
混乱するフランスとアメリカ
――内田さんとお話しされて、いかがでしたか。
おもしろかったし、非常に波長が合いました。内田さんは、もともとはフランス、とりわけユダヤ人問題にかかわるような形で戦中・戦後史をしっかり押さえ、その上でフランス現代思想を専門とされてきたわけですが、今回の対談ではご自身の考えに加えて、イスラーム学者の中田考さんのヴィジョンも組み込みながら語ってくれたので、幅広いパースペクティブで話すことができました。
最初は、どちらかといえば、ぼくがインタビュアーみたいな形で内田さんに話を聞くという感じでしたが、二回目くらいからは、自分の考えを積極的に入れるようになり、結果として、そこからうまく話がかみ合うようになったと思います。
今回の本で意図したのは、いま世界で起きているさまざまな変化を少し長いスパンで位置づけてみるということでしたが、そのために、あえて大風呂敷を広げたところもあります。ただし、こうした鳥瞰的な視点でこそ見える図柄の変化もあるわけですね。内田さんとの対話を通じて、近代的な国民国家がつくり上げてきた制度なり社会なり意識なりが、現在、確実に黄昏を迎えているということが見えてきました。にもかかわらず、それに代わるべきものがなかなか見出せないまま、ある終わりが始まろうとしている――。
ひと昔前なら、「近代の終焉」とか「近代の超克」とかは、居酒屋談義程度のもので、真剣に論じるようなものではなかったわけですが、いまや、それについてきちんと語り得る時代になったということだと思います。何よりも、近代の「正統」と見なされてきたフランスとアメリカに、これまで想像もできなかったような変化が起きている。「はじめに」にも書きましたが、いま、新しいバーバリズム、「二十一世紀の野蛮」としかいいようがないものが、この二つの国に顕著にあらわれています。近代的な自由権、人権を基本原理とした民主主義を生み出した二つの国家、要するに近代の屋台骨みたいなものをつくり出した二つの国家が、どうやら混乱のなかでのたうち回っているというイメージがはっきりとしてきたわけです。
マルクスが言っていますね。歴史は繰り返す――一度は偉大な悲劇として、もう一度はみじめな喜劇として、と。実際、喜劇的な人物がアメリカ合衆国にも登場しつつあるし、フランスにもカウンターパートらしきものがあらわれているのは、そうした喜劇の開幕を告げるものであるかもしれない。それは単なる政治指導者レベルの変化にとどまらず、私たちが近代の一つのモデルと考えていた自由に基づく国家、そして、それによってつくられたシステムそのものが確実に揺らいでいる。そういうなかで、テロに見られるような、ある種の戦闘状態に近いものが至るところで起きるようになってきているのだと思います。
『帝国〈エンパイア〉』を書いたアントニオ・ネグリによれば、エンパイアというのは一つのグローバルな統治システムだということですが、現在世界で起きているのは、そうしたグローバルなシステム全体に危機が遍在化していることの証しでもあります。奇しくも、東日本大震災、熊本地震と数年内に巨大地震が起き、人事と自然の理<ことわり>とがどこかでリスポンスするような日本社会の現状を考えると、いま我々が目にしている一連の出来事は、実は「世界「最終」戦争」の予兆であり、終局的には「最終戦争」へと向かっているのではないかと思えてならないのです。
ポピュリズムなる野蛮の蔓延
――本の中でも触れられていますが、姜さんは現在共同通信で、日本の近代百五十年のエネルギー政策がどのように推移してきたのかを実際に各地を訪ねながらつづる紀行文を連載されています。この対談でも、後半部では、再来年に迎える明治百五十年を念頭に置きながら、明治期の炭鉱労働者から現在の原発労働者に至るまで、日本のエネルギー政策を底辺で支えていた人たちの問題が取り上げられています。日本の近代は、そうした人々をいわば「棄民」として見えない部分に封じ込めてきたが、いまやそうした問題を隠しおおせなくなってきたということを、姜さんは提示されていますね。
そうですね。隠蔽というより、そこにいろいろな形での膜をつくって顕在化しないようにしてきたということで、その覆っている膜は何かというと、戦前であれば戦争で、いまなら経済成長だと思います。
近代国家というのは成長していくことが基本にあるのですが、その成長が止まったときには、さまざまな矛盾を隠しおおせてきたシステムが作動しなくなる。作動しなくなるとどうなるかというと、やはり隠蔽ではなく「排除」という方向に向っていく。場合によっては、そこに国家の持つ暴力装置が露骨に働くことにもなる。フーコー的にいうと、規律権力がまだ働いている時代は何とかうまく処理できたのだけれど、それで近代のいろいろな仕組みを作動させることができなくなったときに、内戦が起きたり、難民が出てくるわけです。
それまで周辺部や外縁部になんとか封じ込めていたのだけれど、まさしくグローバル化の中では周辺や外縁というものが存在しにくくなってきた。そういうところに、政治、経済、社会、文化的な意識形態も含めて、近代の一つの限界がはっきり浮上しつつあるのだと思います。
考えてみれば、冷戦が終わったときには、思ったほどの暴力的な混乱はなく、比較的ソフトランディングできたわけですが、あの時点では近代の体力がまだ保持されていたから何とか矛盾や不満を包摂できたんですね。しかし現在は、その統合と包摂の力が一国内でも萎えてきていて、それが貧困や格差という形であらわれている。これは明らかにある種近代の始まりの時代、つまり、マルクス的にいうと、資本の原蓄(原始的蓄積)過程に限りなく近い状態なんですね。
もちろん、ただ単に近代の始まりが再現されているだけではないけれど、形としてはかなり似通っている。ピケティが『21世紀の資本』で言い表したかったことも、このまま資本主義を放置しておけば、バルザックやディケンズが描いたような時代へと限りなく近づいていくというイメージですね。
そして、最近の、オーソライズされていた企業の粉飾決算が発覚したり、データの捏造が露呈したりするのは、水野和夫さん的にいうと、資本の利潤率がどんどん低下しているからです。資本の利潤率がどんどん低下していくならば、合法、非合法も含めて、さまざまな資本主義的なルールのなかに封じ込められていたものがどんどんディスクロージャーされてくる。
そうしたなかで、安直なナショナリズムがポピュリズムと合体していく。それがかつてであればナチズムになったわけですが、さすがにその亡霊をもう一度呼び出すことはしないでしょう。それでも、ポピュリズムという二十一世紀型の野蛮が至るところに台頭してきているのは事実で、これはかつてのような発展途上国と先進国というカテゴリーを問わず、たとえば今回のフィリピンでの選挙にドゥテルテ大統領というフィリピン版トランプが出てきたように、ありとあらゆるところにある種のポピュリズムが蔓延している。
これは結局、根本的な問題の解決ができないことの、政治的な表出だと思います。こうしたある種の迷妄状態を一時的に引き延ばすことはできるかもしれないけれども、延命すればするほど、むしろ逆に、近代というシステムの崩壊をより速めていくように思われます。だから、内田さんがいうように、いまアメリカで起こっているトランプ現象は、超大国アメリカの事実上の幕引きになっていく可能性もある。そうすると、これまでアメリカのドルを基軸にした通貨や為替のあり方自体も大きく問われてくるはずです。
要するに、近代の始まりにホッブズが描いた自然状態が国境の内と外にぽこぽこと顔をのぞかせていて、それに対する対応がうまくできず、今後さらに、我々が驚くような出来事が遍在化していく可能性がある。だから、今回そういう時代を「世界「最終」戦争」と呼び、タイトルにしてみたわけです。
戦争、震災、統治の正当性とは何か
――かねてから姜さんは、天災、災害とどう向き合うかを、近代はうまく捉えてこなかったとおっしゃっていました。
政治学や経済学、社会学も含めて、人文諸科学は自然災害が持つ巨大な意味を学問的に捉えてこなかった。地震学者とか気象学者とか、理科系の人間たちのテーマではあっても、自分たちとは関係がないというところがあったように思います。
ここで一つ考えなければいけないのは、ピケティによれば、二百年という資本主義の歴史のなかで、第一次世界大戦の始まる一九一〇年代から一九七〇年代の終わりまでというのは、まったく例外の時代だった。その間には二つの世界大戦があったわけですが、大戦を通じてそれまでのアンシャンレジーム(旧体制)が壊れていく。そうすると、第一次世界大戦以前に富を占有していた上層の一〇パーセントから二〇パーセントの人たちが完全に退場して、新しい富裕層が出てきて、富の再分配を図った。つまり、本来不平等の拡大が必然となるべき資本主義の歴史において例外的に格差が縮まったのが、その一九一〇年代から七〇年代までの時代でした。
そして、それはほぼ関東大震災から阪神・淡路大震災までの時期と符合している。つまり、関東大震災と阪神・淡路大震災という社会の基盤を揺るがすような大規模な自然災害――もちろん、そのあいだには相当数の被災者を生んだ大災害が他にもいくつかありますが、とりあえず思想的な影響を与えた自然災害として、この二つの大地震を指標にしたいと思います――に七十年近く直面せずにすんでいた。
ヨーロッパでは、一七五五年、津波で一万人の死者を出したリスボン地震が、イギリスのアダム・スミスやフランスのヴォルテールなどの百科全書派<エンサイクロペデイスト>に多大なる思想的な影響を与えたわけですが、日本の場合も、原発事故まで起きているのだから、その与えている影響は深刻なものだと思います。
ですから、経済的な意味においても、自然災害的な意味においても、この幸福な例外の時期を常態として、それを基準にして近代というものを語ってきたところに、いま直面している言説の無力さがあるんですね。もっといえば、日本の戦後民主主義というものが実は歴史の意図せざる幸運のなかでつくられたということを、いまさらながら実感させられます。
定期的に大規模な自然災害に襲われるということを常態として考えれば、首都直下型地震や南海トラフ地震が起こることは、どこかの国が攻めてくるという蓋然性よりもはるかに高い。そう考えていけば、ホッブズがいった自然状態とは、内戦や戦争という人間同士の戦いだけでなくて、自然災害としてもあり得ることになる。今回の熊本もそうですが、どこを見てもたが<傍点>が外れてしまっています。そういう状況のなかで必死になって日常を取り戻そうとしているけれど、多分戦争と同じように、それを経験した人たちにとって、もう以前のような意識には戻れない。つまり、戦争で受けたトラウマと同じようなことが震災でも起きるわけです。正直いって、我々はそこをきちんと思想化していなかった。
こうした事態に直面すると、これまでのような一元的な主権国家の統治が今後も成り立つのだろうかと考えざるを得ません。実際に熊本の場合もそうですが、東日本大震災のときも、国の介入以前に地域が動いています。たとえば福島の場合には、飯舘や浪江は、国が避難指示を出す前に住民自らが移動している。つまり、一時的ではあれ、国を軸にした主権的な統治のあり方が無力になっているのです。政府は必死になって危機管理の統治権の強化ということをいっているけれど、すでにそうしたことでは対応できなくなってきています。いま起きている九州の地震にしても、もし今後万が一の危機に陥ったときに、国が実際に動く前に、九州のほうで広域的な動きに出ることだってあり得るでしょう。
つまり、これまで近代国家は立憲主義的な正当性をもって機能するような仕組みをつくってきたけれども、いまはその正当性の調達が、日々困難になりつつあります。むしろ、むき出しの力の行使によって実効性を担保しようとしているのではないでしょうか。だから立憲主義というのはもはや建前で、実態としては空虚な言葉になりつつあるという状況です。我々はそこをしっかり見抜いていかなければならない。
今回、そのあたりのことを忌憚なくずばずばといったわけですが、そうできたのも、やはり相手が内田さんだからこそですね。もしかすると、ここで語られているのは極端な議論だという批判があるかもしれません。しかし、極端ではあれ、フィクションに近いヴィジョンを立てることで、見えてくるものもあるはずです。その辺を読み取っていただければ嬉しいですね。