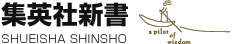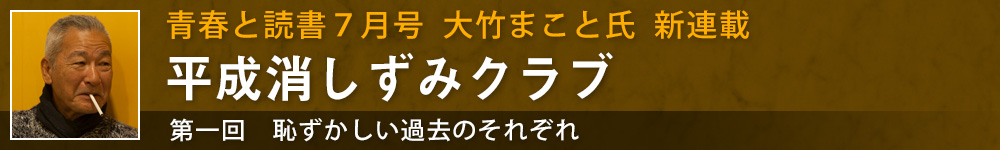連載スタートを記念して、第一回を特別に掲載いたします。
梅の花がハラホロヒレハレと散って、地べたに何かを描こうとしたが、それを風がはこんで、溝に小さな川が出来た。
文化放送の月曜から金曜まで、昼の帯番組のラジオが始まって、あっという間に十年が過ぎた。
もう六十八歳になった。いやはやである。
お話を頂いた時には、まあやっても二〜三年かなと思っていたのだが、今日まで続いてしまった。
いまだに、己の所在さえ掴めぬ私が一体何をしゃべってきたのか。
ある時は、分をわきまえず「俺がラジオだ」とまで叫んだ男である。全く、恥ずかしいったらありゃしない。
ゲストの話もロクに聞かないし、自らの話は、始まった当初よりずっとまとまりがない。時間通り終われず、尻切れトンボで終了の午後三時三十分になったりする。
坂道や階段でつまずくならまだしも、平らな道さえ、うまく歩けない。辻がくれば、かならずカタをぶつける。
「君は、ラジオを聴いている人の身になったことがあるのか?」
と誰かの声が聞こえたが、空耳だったかもしれない。
先日、作家の大沢在昌さんと御一緒する機会があり、「あること、ないことしゃべってきた」と話したら、「私もそうだ、気にするな」と慰めてくれた。良い人である。
さすが三十八年も物書きをやってきた人の言葉には、説得力がある。
丸々信じてしまいそうになった。
しかし、この場所は、今から五十年前、高校生だった私が憧れていた場所でもあるのだ。
当時は、ラジオ深夜放送の全盛期であり、多くの高校生(受験生)が夜中のラジオにかじりついていた。
私もその一人で、野沢那智と白石冬美の放送をよく聴いた。
「赤白ピンク」というラジオネームの投稿者がいて、彼の葉書がよく読まれていたのを、今でも覚えている。
私も何度か投稿して、ドキドキしながら聴いていたが、読まれる事は一度もなかった。
いつか、私もラジオのディスクジョッキーになりたいと大胆な夢を描いた。
しかし、ロクな勉強もせず怠けていた私が大学に受かる【筈/はず】もない。全ての大学を落ちて、浪人生活に入るのだが、親にもらった【代/よ】ゼミ(予備校)の入学金をちょろまかしてから行き場を失った。
そして、私は街のチンピラになった。
駅前の【雀/ジヤン】荘に入り浸り、パチンコに明け暮れ、たまにバイトもした。工事現場の日雇い、六本木のクラブのボーイ、西銀座のスナックでは一度使ったミネラルウォーターの瓶に水道の水をジャジャと注いで、元通りにうまく栓をした。新橋のクラブのママは、石原裕次郎気どりでピアノの弾き語りが上手い【髭/ひげ】の濃い客に全部を貢いでいた。
若い私が飛び込んだ社会は、ダメな大人達の溜まり場のような所だった。もちろん私はそれに輪をかけた馬鹿でもあった。
その日暮らし、一体、何がしたくて生まれてきたのか。
街の女達とも、すぐに仲よくなれた。いや、若くて何者でもない私は、彼女達にとって、都合のよい遊び相手ではなかったかと今にして思う。
何人かの女達は、就職が決まったとか、ちゃんと結婚することになったとか言って、皆、離れていった。十八のチンピラとまともに付き合う女はいなかった。ただそれだけの話だ。
社会に貢献する気も、生きるに値する価値も見出せなかった。
そして、もう一つ小さな理由があった。
【僅/わず】か十七歳で亡くなった同級生Kのことだ。
高三の冬、受験をひかえた私に一枚のクリスマスカードが届いた。そして、年が明けた一月二十五日に、カードの送り主のKは、あっけなく死んでしまった。
私は、その少し前、友人達と東大病院に入院していたKを見舞った。
友達以上の仲ではなかった。三年C組の私の一つ斜め前に座っていたのがKだった。
私は、ノートや教科書、エンピツまでもよくKに借りた。Kはとても静かで、当時にはめずらしい黒縁の眼鏡が似合う子だった。
人は簡単に死んでしまう。
私は葬儀の席で、人目もはばからず、大声で泣いた。泣きながら西武線の線路沿いを駅まで歩いた。人に奇異の目で見られた。
身近な同級生が、この世から消えてしまった。明日から、もう朝の挨拶も、気軽な冗談も言えない。下校の時、その後ろ姿を追う事だって出来はしない。
こんな理不尽な事が起こってよいのか、私も、多分、何かで簡単に死ぬのだろう。
早く死ねば、早くKに会える。
おっと、話が濡れてしまった。その後にいろいろな事情があって、私はこの業界の近くをウロウロしていた。
初めは、どさ回りのコメディアンであった。気楽で良かった。【暫/しばら】く肝臓病を【患/わずら】って入院していた、コメディアンの山本修平(これが私の本当の師匠)さんが回復して、相方を探していた時に、先輩に紹介されたのが縁で、地方のキャバレー回りの相方をすることになった。
ネタは「斬られの与三郎」「貫一とお宮」とか十本くらいあったが、最後の落ちは皆同じだった。
着物とカツラをまとった師匠が女形で曲とともに舞台に登場し一踊り、後から出た私が着流しなんかで師匠に文句をつける。その間に女形の師匠は、ホステスを蹴散らし、客のビールなどを勝手に飲んで笑いを取る。
私に【匕首/あいくち】で胸を刺されると、着物の合わせ目から布地の血が出て、その先に万国旗が繋がって出てくる。
最後はブラジャーとパンティになってコントが終わる。
北海道、東北、関東。当時はキャバレーが全盛期で、テレビに少し出て顔を売って、地方で稼ぐ、それが芸人の王道であった。
サムライ日本、ミュージカルぼーいず、てんぷくトリオにコント・ラッキー7。
土地それぞれのホステスさん達に書生さんと言われて、かわいがってもらった。北海道では、一○八センチのバストの女に乳の間に顔を埋められ息が出来なかった。死ぬほど楽しかった。
そしてラジオが始まった。十代の頃、私が夢にみた、ディスクジョッキーである。今は呼び名も変わってMCとか言ったりするらしいが、違う、ディスクジョッキーである。
振り返れば、チンピラからドサ回りのコメディアン、その後、新劇の養成所に入り、アングラ劇団を立ち上げ、食うや食わずでコントグループ(シティボーイズは今も解散していない)を作る。ピンでテレビに出るようになってからは、コメンテーターと呼ばれたりもする。
本当に勘弁して下さい。
高校時代の同級生は、私が役者になったと驚き、役者仲間は、あの大竹がコメディアンになるとは誰も想像していなかった。
それが五十七歳を過ぎてラジオのパーソナリティ(ディスクジョッキー)になった。
一番驚いているのは、誰であろう、この私である。
そして、お世話になった人々が、今の私に語りかけてくる。
私は、それを音声に乗せて皆と共有しているだけである。 子ども時代の小心な私、イジメっ子、かばって助けてくれた修ちゃん。
ヘタな絵を褒めてくれた先生、柿泥棒の友達、駅前の喫茶店でいつもモーニングセット(トースト食べ放題)をおごってくれた雀荘のマスター。小遣いをくれたヤクザ。
一緒に逃げた雅昭、小田原の女、【二十歳/はたち】から二年半、一緒に住んだ風間杜夫。
恥ずかしい過去のそれぞれは、立派な笑い話になって、電波に乗ったりもする。
過去の私が、今の私を笑っている。
「K、聞いてるか、ハラホロヒレハレと梅が散った。俺がラジオだ」
(2017年06月20日掲載)